「受容する力」「何もしない選択」
こんばんは。だにー。です
最近読んだ書籍の中面白いな、と思った概念があります。それは「ネガティブ・ケイパビリティ」と呼ばれる概念です。この概念について、少しでも身近に感じられるように、業務の話も交えて記載してみようと思います。
読んでみて欲しい方
- 若手社会人の方
- すぐ焦って取り乱してしまう方
チラつく不確定要素。。。
この概念について説明するにあたっては、何か問題が発生した時を想定するとわかりやすいと思います。私の専門がIT業界という事もあるので、その業務の中で度々実施する「リスク分析」についての話を交えながら記載していこうと思います。
100%確信を持った正解というものはなかなか存在しないもので、少しでも何か「リスク」や「懸念」が存在する場合には、「YES」「できる」とはなかなか言いづらいものです。
これは周りからすればなかなか沸きらない答えであり、「大丈夫か??」と不安にさせてしまう要因となることは間違いないと思います。
勿論そこは社会人なので、断言しないといけない場面も多々ありますし、このコミットを何が何でも達成する。この積み重ねにより信頼が生まれ評価に繋がる、という会社が多いと思います。
※勿論、数字で定量的に測れる評価制度があれば一番分かりやすいですね。
「やります」と言ったからにはやりきらなければならない。しかし、そこには予想外の出来事がよく起きるものですよね。。。
日々の業務につきまとうリスクについて、以下2つの分類で考えてみます。
- 想定内のリスク
- 想定外のリスク
想定内のリスク
想定内のリスクとは、事前に考え対策を検討できるものです。私は普段IT関連の業務に従事しており、プロジェクト開始前にこのリスク分析を嫌と言うほど実施します。
- それぞれのフェーズにおいてどのようなリスクが考えられるか?
- そのリスクが実際に発生した場合、どのようなインパクト(損失)があるか?
- 発生しないために、どのような対策をとるか?
- 発生した際にはどのように対策するか?
嫌と言うほど、偉い人から詰められます。笑
それぞれに対して「回避」「軽減」「移転」「保有」といった考え方を持って、備えるわけです。こうして対策まで事前に整理できたものについては「想定内のリスク」となり、いざ発生した際にもうろたえず対応できるようになります。
想定外のリスク
続いて想定外のリスクについて記載したいと思います。
「想定外」と言うほどなので、要因は本当に様々です。それはヒューマンエラーであったり、システムエラー(バグ)であったり、顧客の気変わりであったり、あげるとキリがない程です。
中でも、「なんでそんなことが起こるのか理解ができない」と言うものに出会った時、それに対する対応や心境については人によって様々になります。
「人のせいにする」
「とりあえず何かしなきゃとテンパる」
「思考停止する」
私が見てきた限りでは、「とりあえず何かしなきゃとテンパる」人が多割と多い印象です。
次いで「人のせいにする」なきがします。
冒頭でも記載した通り、「やる」とコミットしたことをやり切る(有言実行)こそが一番わかりやすい評価軸であり、それを妨げる障壁となる事象が発生するわけですから、どうにかその状態から逃れるために色んな葛藤が生じます。
何か問題が発生した際に一番効果的なのは、「いかに早く最善の手をうてるか」と言う点です。
「早く手をうつ」にとらわれた結果、有効な手をうてず余計ややこしい状況になったり、「人のせいにする」「思考停止する」など行動を起こさない事で何も解決しなかったり。このような状況においてバランスをとった行動をするための参考となるのが「ネガティブ・ケイパビリティ」です。
ネガティブ・ケイパビリティ
これについてはいくつか書籍も読んでみました。後日、その書籍などについての紹介もしたいと思うので、詳しくはその際に。。。
「ネガティブ・ケイパビリティ」とは、一言で言うなれば「よくわからない事を受容し、耐える力」です。
「なんだそんな事か」と思う人も多いかもしれませんが、これがかなり難しい事ですし、人によって向き不向きもはっきり分かれる事だと思います。
何かよくわからない事が発生した時に、それを受け入れ向き合うのです。その中で何が最善かを考える。時には「今は何もしない」と言う答えにたどり着く可能性もあるのです。
ケースバイケースではありますが、この選択肢もあり得るという事を理解しているのとしていないのでははっきりと差が出てくるはずです。
何がなんだかわからない事態を受容し、放置するんです。人間関係においては「時が解決する」と言う言葉など、よく聞いたことがあると思いますが、それに近いこともあると思います。よくあるのだけれど、ビジネスにおいてこのような決断は評価されづらいと言う実態もあります。
やはり企業においては、勢いがあり目立つ「動」の存在こそが評価されやすいのです。
反して、この概念は受け入れ、すぐに動かず、じっと耐える、「静」の概念に近いです。
このような概念を理解し正しく実践できるような人こそ、いざという時に頼られる人なのではないかな。と考ています。
終わりに
みなさんはこの「ネガティブ・ケイパビリティ」について、どう思いますかね?
聴き慣れない言葉ですし、「ネガティブ」というフレーズから、あまりいい印象は持たないかもしれません。しかしながら、身近にこのような能力に長けてる人がいて、その人の事を想像したりしませんでしたか?
多分ですが、その人は職場やその団体において信頼され、一定の支持を得ている方ではないでしょうか?
もしかするとその方もこの概念に触れ、影響を受けた方なのかもしれませんね。
余談・・・・「あいまい」に考える
「あいまい」と言うと、何か煮えきらないような、歯切れの悪いような、ネガティブなイメージを持つかもしれません。
しかし、時には白黒決めず、答えを出さず、あいまい(グレー)なまま捉える事も1つ訓練になるのかな?と言いう事で、「あいまい」に考えるというテーマをつけ、このブログを記載してみています。あくまで時事ネタなどに対して、何か結論づけず、こういう考え方もあるんじゃないかな?という課題提起ができればいいな、と考ています。
つまりは、いろいろな角度から物を見れ、想定外の事態や価値観などに出くわした際にも動じず然るべき対応を取れる。そんな人間を目指してみています。
そこから何か、みなさんからレスポンスを頂けると更にいいブログになるなぁ、と漠然とした理想を持っていたりもしますが。笑
勿論、専門分野などで役立つ情報なども載せていければいいな、と考ています!
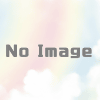
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません