テレワークの実態について考えてみる
こんばんは。だにー。です。
コロナウィルスの影響により、海外のみならず日本全国においても非常事態宣言が発出され、外出、人との接触など控えるよう自粛宣言が出されていますね。
多くの企業が在宅勤務、いわゆる「テレワーク」を実施しており、テレビ番組なども電話出演や、Microsoft社のSkypeを利用したテレビ電話で出演している光景が珍しく無くなってきました。
その中で課題として取り上げられているのが、一般企業におけるテレワークの実施率です。
今日はこのテレワークについて、現役SEの目線からお話したいと思います。
かなり主観も混ざっていますので、こういう考え方もあるのか、という目でみていただけますと幸いです。
今日の記事については下記の方々に目を通していただき、何か少しでもプラスになってくれると嬉しいです。
- 他社の実施しているテレワークなどの情報が欲しい方々
- ITに興味のある方々
- 企業に所属しておらず、「なぜテレワークができないの?」と疑問を持っている方々
- 学生の皆様
目次
- 現在の主要都市におけるテレワーク実施状況(2020年4月20日時点)
- そもそもテレワークってどうやるの?
- テレワーク実施を阻害するのはなに?
- 総括
現在の主要都市におけるテレワークの実施状況
日本のテレワークの実施状況について見てみましょう。
【実施率】
東京:49.1%、神奈川:42.7%、千葉:38%、埼玉:34.2%、大阪:29.1%
(全国平均:27%)【推奨・命令している企業】
東京:64.7%、神奈川:57.7%、千葉:51.7%、埼玉:47.3%、大阪:43.5%
(全国平均:40.7%)【アンケート対象】
ITMedia News
調査は4月10〜12日にインターネット上で実施。従業員数が10人以上の企業で働く、20〜59歳の男女2万5769人
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2004/17/news103.html
最大で東京の49.1%とあります。詳細な数字などについてはリンクを参照いただければと思いますが、この数字について、どのように思うでしょう?
人によっては少ないとも感じると思いますし、多いとも感じるかもしれません。
この数字の抽出前提が詳しく記載されていませんが、もしかすると「テレワークを実施している(たまに出社もするよ)」という人もカウントされているかもしれませんね。
次に、企業がテレワークを推奨、もしくは命じている数字を見てみましょう。
東京においては64.7%の企業が推奨・命令しており、全国平均においては40.7%とのことです。
この数字についても人によっては少ないと感じると思いますし、多いとも感じると思います。
なぜ推奨・命令を出してない企業があるの?と疑問を持つ方もいるかもしれません。
私の予測ではありますが、この割合は
「テレワークを実施できる環境、もしくは制度が整っている企業」と近しい数字になっているのではないか
と考ています。
勿論、事前に整備できていた企業もあれば、急ぎ整備し無理やり実施している、という企業もあると思います。
企業が推奨・命令している割合と比較して、実施率についてはそれぞれの地域で約10〜15%程度低くなっています。つまり、推奨・命令をしている企業においても、それなりの人数が出社している(恐らく2割〜3割程度)という事です。
国外のテレワーク実施率の数字も欲しかったのですが、参考情報が見つからず、比較できないのがもどかしい。。。
そもそもテレワークってどうやるの?
各企業はどのようにテレワークを実施しているのでしょう?
実際にインタビューなど実施しているわけではありませんが、現在の「IT技術」をもとに考られる働き方を記載していきたいと思います。
OA環境について
最初に、どのようなOA環境で業務を実施しているか、という観点で記載してみます。
- USB等でデータを持ち帰り自宅用のPCで実施
- 会社のPCを自宅に持ち帰り、そのまま実施
- 会社のPCで実施。業務に応じてVPNなどで社内システムに接続
- シンクライアント端末からVDI環境に接続し業務を実施
よくある例とすると、このあたりでしょうか。
「1.」の例については説明不要かと思います。
「2.」の例については、実はただただ普通のPCを持って帰り業務をしている企業と、各種クラウドサービスをうまいこと組み合わせてかなりお金のかかったOA環境を整備している場合もあります。後者についてはまさに「最前線」の業務環境だと考えていますが、このような業務環境を整備できている企業は日本にはそうそうありません。笑
(そのうち、この件についても記事にできるといいな。。。)
「3.」の例についてはそれなりの大きさになった会社では主流かもしれません。
オンプレで構築された社内システムなどを持ち出す事はできないので、「VPN」という通信技術を用いて社内ネットワークにアクセスし利用するというパターンです。
「4.」の例については、いわゆるお金のある企業が整備している環境となります。
シンクライアント端末(Thin Client)とは、必要最低限のソフトのみをインストールし、WriteFilterという機能を有効化したWindows端末です。
この端末だけではなにもできませんが、データセンター上に構築されたVDI環境にリモートデスクトップ接続する事で、あたかも通常のPCを利用しているかのように業務を実施できるようになります。
VDIについて説明し出すとその方式などかなり技術に寄った話となってしまい、かなり長くるため今回は割愛させてください。。。
打ち合わせとかはどうしてる?
日本企業の多く(特に大手企業)は、「打ち合わせ」に膨大な時間を費やしています。恐らく1日の半分以上が打ち合わせという人も少なくないと思います。
こちらについて、現在テレビでもよく見かける「テレビ会議」を開催している企業がほとんどかと思います。
テレビ会議を実施するためにも勿論、専用のシステムが必要になります。例えば、
・Skype
・Zoom
・WebEX
・HangOuts Meet
あたりが主流でしょうか?
(Zoomは最近いろいろありましたね。。。)
基本的にはPCで表示している資料などをテレビ会議参加者と画面共有をしながら実施する事となります。
ここまで記載させていただいた情報からだけでも、それなりの準備が必要ということがなんとなく想像できたのではないでしょうか。これはあくまでIT技術面のお話です。しかもこれは本当に極々一部でしかなく、実際にテレワークを実施しようとすると色んな課題が出てくる事となります。
テレワーク実施を阻害するのはなに?
メディアでも取り上げられている情報、これまで記載したOA環境などからなんとなく想像がついている部分もあるかと思いますが、具体的には何がテレワークを実施する上での障壁となっているのでしょう?
この部分について切り込んでみたいと思います。
結論から申し上げますと下記要因が大部分を占めると考えています。
- 情報セキュリティ
- ルール
- 紙の文化、はんこの文化
- 古き文化と固定観念
情報セキュリティ
テレワークにおけるOA環境いついて触れさせていただきましたが、そもそもなぜ専用にシステムを設けないといけないのでしょう?
もちろん効率的な業務を実施するため、という事もありますが、何より重要視されるのはこの「情報セキュリティ」です。
「個人情報」「機密情報」を取り扱うにあたって、これらを悪意あるユーザの攻撃により流出させるわけにはいかないのです。従業員のミスであっても、流出する事で損害賠償が発生したり、社会的影響を受け多大なダメージを企業はうける可能性があります。
そのために先述にもある「VPN」「VDI」というような仕組みを用いて、「社内で情報を取り扱う際と同等のセキュリティ」を担保しようとします。
日本はとりわけこの「情報セキュリティ」に対してのルールが厳しく、メールにファイルを添付しようものなら必ずパスワードをかけるという企業が多いのではないでしょうか?
この「情報セキュリティ」を担保するためにはお金をかけてシステム的に情報を守る必要があり、お金がかかるのです。大手などの企業についてはお金もあるので、このテレワークを実施するための業務環境が揃っている事が多いかと思います。その分、中小企業以上に守らなければならない情報が多いため、よりセキュリティを高めるようなシステムとなっており莫大なお金がかかっています。
そもそも社内ネットワークが安全、という考え方も古い気がしますが、、、
情報漏洩はヒューマンエラーでの発生が一番多いとのデータもあります。
ルール
次に記載するのは「ルール」についてです。
何のルールか?というと、「労務管理」「テレワーク実施」におけるルールだと考えています。
労務管理について先に記載します。36協定など、企業は遵守した上で従業員を雇い業務を実施しないといけません。
一番わかりやすいのは「労働時間」の管理です。目の届かない所で仕事をするのですから、タイムカードやビルのゲートなどで労務管理を実施していた会社からすると、誰が何時間働いているのかが見えづらくなるのです。管理者の目の届かない場所でサービス残業をする事で、この鉄の掟を逸脱する社員が出てくるかもしれません。
逆にサボって働いたふりをする、なども定量的な業務評価制度のない企業からすると気にしているポイントかもしれません。
次にテレワーク実施におけるルールです。
これは至ってシンプル、何を持ってテレワークを実施可とするか、という「決め事」です。
日本企業の戦士はとてもお行儀が良いので、ルールがないと動けない、と言う人が少なくありません。決めればいいじゃん!と思うかもしれませんが、今まで記載した「情報セキュリティ」「労務管理」を満たすためにはどうすればいいかを「決めれる人がいない」パターンが多いかもしれません。情報セキュリティについては専門知識がないと妥当かの判断がつかないということで何となくわかるかもしれませんが、単純に「誰が」「どのような承認フローで」決定するというのがわからず検討が進まない企業も多いのかもしれません。
紙の文化、はんこの文化
はい、日本はいまだに紙&はんこ文化なのです。。。
これは前半で記載している、「推奨・命令をしている企業においても、それなりの人数が出社している(恐らく2割〜3割程度)」という部分に関連する話でもあります。
・郵便物(紙)を受け取るために出社する人がいます
・書類を印刷/スキャンするために出社する人がいます
・書類にはんこを押すために出社する人がいます
なんじゃそりゃ、という例を3つ記載しましたが、一番邪悪なのが3点目の「はんこ」だと思っています。「紙の郵便物がなぜ送られてくる?」「そもそもなぜ紙に印刷しないといけないのか?」「なぜスキャンする?」。。。はい、お察しの通り、はんこを押すためです。。。
日本のIT大臣が変わらないとこの問題は解決しないかもしれませんね。。。
DocuSignをはじめ、世の中電子署名のための便利なサービスもあるというのに。。。
古き文化と固定観念
私達を取り巻く環境、特に技術は凄い勢いで進化しています。この進化についていけない人達がいます。それは「年配者」に多いです。
紙とはんこで仕事し、デスクで隣のせきの人と喋りながら、会議室で多くの時間を過ごす。
これが今までだったんです。変化を受け入れるのはかなり力がいることです。しかし、企業の意思決定に携わる役職の人は、「年配者」の割合が多いことでしょう。
変化を嫌う人が一定数いると思いますし、その結果、配下の社員たちはその人に合わせないといけず、テレワークを実施することに積極的になれない、という問題が起きていると思います。
また、よく聞く理由として「出社しないとできない仕事」というものがあります。
本当でしょうか?多くは「思い込み」と「固定観念」ではないでしょうか?
少しの工夫で、テレワーク でも実施できることじゃないでしょうか?
「古き文化と固定観念」という題で記載させていただきましたが、歴史ある企業ほど、この影響をうけるのではないかと思います。国会などまさにそれかと思います。
総括
好き勝手書かせていただきましたが、どう感じましたでしょうか?
私は今がまさにターニングポイントだと考えており、今後大きく世間が変わるのではないかと考えています。
テレワーク環境の重要性が増すとともに、新たな課題が見えてくると思います。
テレワークの普及に伴い、「移動」というものの価値が見直され、出社など不要な移動は無駄なコストと割り切る企業も増えるかもしれません。その結果、「どこにいても仕事ができる」という社会が形成され、東京の会社に所属していても沖縄に住んでいる、と言った「住」の多様性が生まれるかもしれません。これから就活を実施する学生からすると、企業選定の基準として重要性も増すことかと思います。
現在自粛によって辛い思いをされている方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、これがまさに次の時代の幕開けなのかもしれませんね。
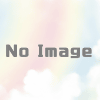
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません